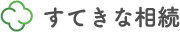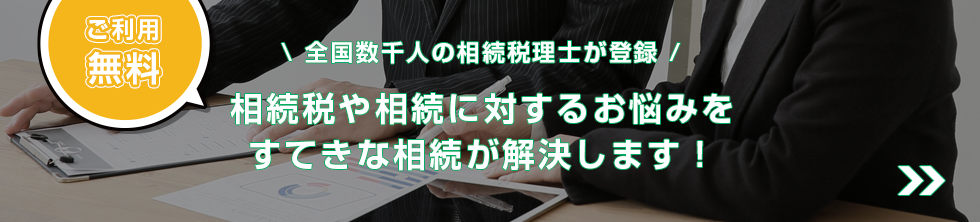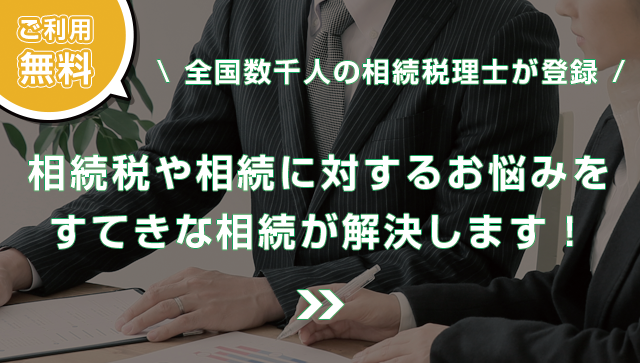2019年8月23日 金曜日
相続税申告を税理士に依頼、費用はいくら?税理士の選び方も
税理士に相続の依頼をすると、費用はどのくらいかかるのだろうと、不安に思われる方もいらっしゃると思います。
相続税が発生する機会は一生に1、2回あるかどうかですが、せっかく残してくれた財産なので、できるだけ相続に関わる税金は低く抑えたい、と考えている方も多いでしょう。
税理士によって費用が大きく違うこともあるので、普段から税理士と接点がない方は、何を基準に税理士を選べばよいのでしょうか。
今回は相続が発生した時、税理士に依頼するメリットや費用、選び方をご紹介します。
目次
相続税申告を税理士に依頼するべき理由とは?

相続税の申告は相続が開始してから10カ月以内に行い、納税しなければなりません。
納税は国民の義務ですので、怠った場合の罰則は厳しいものになっています。
期間内に納税できなかった場合は、延滞税に加えて無申告加算税または重加算税、過少申告加算税のいずれかを支払うことになります。
急いで申告したり間違って申告したために、相続税を多く払いすぎたり少なく払ったりすることがあるかもしれません。
期限内に納税したとしても、税務調査により少なく払ったことを指摘された場合には、追徴課税を支払うことになりますので注意が必要です。
相続に関する申告は、誰が行っても納税額が同じ金額になるとは決まっておらず、専門的な知識を要します。
間違いなく期限を守って行うために、また相続税を抑えるためにも、相続の専門税理士に依頼することをオススメします。
正確に申告を行うため
相続税を多く納めすぎた場合は、更正の請求をすることで相続税の還付を受けられます。
更正の請求には期限があり、遺産分割のあったことを知った日から4カ月以内となっていますので、期限内に手続きを行いましょう。
また申告後にプラスの財産が発覚したなど、納税額が不足していることが判明した時は、修正申告をして足りない分を納税します。
修正申告に期限はありませんが、申告時期や状況によってさまざまな追徴課税が発生します。
申告期限内に修正申告した場合は、不足分の納税のみですが、10カ月を超えて自主的に申告すると延滞税が追加で発生します。
しかし、修正申告を行わず、税務署の調査で申告に誤りがあることを指摘された場合は、延滞税に加えて過少申告加算税を納税しなければなりません。
さらに税務署が意図的に納税額を過少申告したと判断した場合は、延滞税に加えて重加算税が発生します。
そして、そもそも申告をしていないことを税務署から指摘された場合は、延滞税に加えて無申告加算税が加わってしまいます。
自力での申告は時間がかかるため
自分で相続税の申告を行うことも不可能ではありません。
一般的に納税額が少ない場合には、税理士に依頼せずに納税者本人が自力で申告することがあるかもしれません。
しかし国税庁が作成している相続税のパンフレットは、100ページ以上にわたりますので、自力でやるには専門性が高い相続税は、難易度が高いでしょう。
土地の相続がある場合、正確に土地の価値を計算しなければなりませんが、相続において土地の評価は非常に難しく経験と知識が必要と言われる項目の1つです。
また、総額1億円以上を相続することになる場合は、少しの誤りが大きな差額となりやすいです。
相続財産額の計算は、相続する種類や数によって、時間がかかることが予想できます。
どのような財産があるのか正確に把握しており、自分で財産価値を判断できるのであれば、自力で申告することも可能かもしれません。
しかし、自力での調査は時間がかかるでしょう。
期限内に相続税の申告・納税ができなかった場合、相続税以外の費用がかかってしまうので、自力で申告を行うか、相続の専門家に依頼するかは早めに判断することをオススメします。
節税についても相談できるため
相続税をなるべく低く抑えたいと考える方は多く、「残される遺族のために、少しでも相続税を抑えてあげたい」と思う方も少なくないでしょう。
節税対策には以下のようにさまざまな方法があります。
・不動産を購入する
・毎年110万円を贈与する
・生命保険の非課税枠を利用する
・賃貸アパートを購入する
・お墓や仏壇を生前に購入する
・養子縁組を活用する
節税の仕方によっては、何百万単位で相続税が変わる場合もあります。
さまざまな節税対策を行うためにも、できれば相続発生前から相続の専門家に相談しながら対策することをオススメします。
相続税申告を税理士に依頼!費用の相場は?
以前は税理士報酬の規定があり、基準が定められていたため、どの税理士に依頼しても費用は大きく変わりませんでした。
しかし、現在では自由に費用を設定できるように規定が変更になっています。
税理士によって費用の設定はさまざまであり、以下の内容で費用を決定している税理士が多いでしょう。
・相続財産額に対して何%を費用とする場合
・相続財産額を段階的に分けて費用を決めている場合
適切に申告を行っている税理士の相場はだいたい決まっていますが、ここでは費用の相場と注意点について紹介します。
相続財産額の0.5~1%が相場
一般的に相続税申告の費用は相続財産額の0.5%~1%が相場と言われています。
基本の費用に、相続した財産の種類によって加算する場合もあります。
土地や株式の相続は、知識や経験で相続税額が大きく変わる可能性が高い分野です。
この分野が相続に含まれる場合、費用を追加されることがありますが、合計して概ね0.5~1%の費用に設定している税理士に依頼することをオススメします。
費用に大きく差が出る場合は、他の税理士にも相談してみるなど検討しましょう。
安さで選ぶと思わぬ落とし穴も
費用が、他の税理士に比べて明らかに安い場合、主に以下の理由が考えられます。
・価格競争によるもの
・担当者が税理士ではなく補助者
費用が自由に設定できるようになったため価格競争が起こり、税理士によっては費用を安く抑える可能性は十分にあります。
しかし、その他の理由は、申告ミスにもつながりかねません。
また、税理士事務所には税理士資格のない方もたくさん勤めています。
相続税の申告の費用が安い理由が、税理士ではなく、補助者が担当となって代わりにチェックシートなどを用いて聞き取りする税理士事務所も、ごくまれに存在するようです。
税務調査で申告漏れが発覚した場合、加算税や延滞税などを払わなければならなくなります。
税理士に依頼する時は多少の費用は覚悟し、どのくらいの経験があるか、税理士に最後まで担当してもらえるのかを確認するようにしましょう。
税理士の選び方とは?

通常、相続税の支払いは一生に1、2回あるかどうかです。
その相続税の相談を誰にするか、税理士と接点がない人にとって悩ましいところですが、まずは税理士を選ぶ方法を考えることから始めなければなりません。
そこで、税理士を選ぶためには、何を基準にどの税理士を信じたらよいのかを判断するポイントや注意点を紹介します。
適正価格で、明朗会計の税理士を選ぼう
前述したとおり、税理士の適正な費用は相続財産額の0.5~1%と言われています。
この費用ですが、単純に上記の割合で費用を提示する良心的な場合と、話を進めるうちに費用を次々と追加する場合があります。
追加の費用の項目として例をあげます。
・不動産の項目で相続税を1000万円減額したため、30%を追加の費用として加算
・相続税以外の、口座の名義変更を依頼したため追加で費用を加算
などのケースで、最終的には予定の費用よりも跳ね上がる可能性があります。
相続の専門家に依頼する時は、追加やオプションにかかる費用を確認するようにしましょう。
税務調査率の低い税理士を選ぼう
書面添付制度という制度をご存知でしょうか。
書面添付制度とは、相続税の申告書の作成に税理士が関わっており、申告漏れはないことを証明する証明書のようなものです。
相続税を申告する時に添付することで、申告内容の信頼性が高まる効果があり、税務調査が行われる確率が低くなるメリットがあります。
一般的に、税務署から税務調査を受ける確率は、約10~25%ですが、書面添付制度を利用すると10%以下になると言われています。
さらに申告内容に疑問がある場合は、担当税理士だけが税務署に呼び出され、そこで確認が取れると、税務調査は行われません。
通常税務調査により申告漏れが発覚した場合は、加算税や延滞税が追加されますが、税理士により確認が取れた場合は自己申告と判断され、延滞税のみ支払うことになります。
さらにこの場合、相続の発生から10カ月以内であれば、延滞税も発生しません。
しかしこの制度を利用していない場合もあります。
それは、書類に嘘の記載があった場合、税理士は懲戒免職となってしまうからです。
相続に自信のない税理士は、書面添付制度を利用しない可能性があります。
したがって、専門家に依頼する場合は、費用がかかるとしても書類添付制度を利用できる相続の専門税理士であるかを確認すると良いでしょう。
相続税申告が得意な税理士を選ぼう
主に法人税などを担当する税理士が多く、相続を専門としている税理士はごく一部と言われています。
インターネットで検索すると、相続の専門と謳っている税理士事務所がたくさんヒットします。
その際、本当に相続が専門なのか、よくチェックしましょう。
相続に関する依頼の年間件数や、税理士の人数も必ず確認する必要があります。
例えば、年間件数が100件だとして、税理士事務所にいる税理士が100人いる場合と10人いる場合では、一人当たりの担当件数に差が生じます。
他の税理士に比べ費用が高くなるとしても、相続の専門なのか、一人当たり何件程度担当しているのか、確認し依頼するようにしましょう。
実績の多い税理士を選ぼう
相続税に関して、税理士の実績件数は大きく差が出ます。
理由は、相続が発生する件数の差にあります。
税理士には、法人税や所得税、消費税などのように、相続税以外にも専門分が多くあります。
法人税などは、法人化した企業が毎年支払う税金であるのに対し、相続税は相続が発生した時にしか納税しませんので、発生件数には雲泥の差があることは明白です。
実際、国税庁のホームページでは、平成28年度の相続税の課税対象者となった被相続人数は、約10万6000人と発表されています。
日本税理士会連合会のホームページによると、令和元年時点の税理士登録者数が全国に約7万8千人いるということなので、単純計算で税理士1人あたり年間1.3人しか担当していないことになります。
これらの数字からも、相続専門の税理士が希少であることがわかります。
相続に関しては、知識と経験が特に重要な分野です。
費用がかかるとしても、できる限り経験の多い相続の専門家を探し、依頼するようにしましょう。
税理士への相談はいつ行うべき?
結論から言うと、早ければ早いほど良いでしょう。
相続発生前から相続税対策を税理士に依頼しておくことで、不動産購入や生前贈与などの節税対策を十分に行うことができます。
また、相続発生前に依頼することで、費用は依頼者が支払います。
相続税は現金一括で支払うため、その費用を残しておかなければならない相続人の助けにもなります。
相続発生に伴う申告などの期限はさまざまなものがあります。
①相続放棄、限定承認は3か月以内
②準確定申告は4カ月以内
③相続税の申告・納付は10カ月以内
特に、相続税の申告や納税が間に合わない場合、無申告と判断され、延滞税や無申告加算税を払わなければなりません。
相続を放棄する場合も、相応の調査をしてからでないと判断できませんので、十分な調査期間を得るためにもなるべく早く、できれば相続発生前から相続の専門家に依頼することをオススメします。
まとめ
税理士に依頼する場合の費用や、信頼できる税理士を選ぶポイントを紹介しました。
相続する種類が多いと相続税額も高額になりやすいでしょう。
しかし相続財産額が高額であるほど、税理士の知識や経験によって節税対策が大きく変わってきます。
特に土地の相続は、税理士の鑑定によって何千万円単位の差が出ることも珍しくありません。
ある程度の経験がある税理士に頼む場合は、費用が高額になるかもしれません。
その代わり、土地の評価価格を低く抑えたり、生命保険の非課税枠を利用や、墓地や仏具の購入、生前贈与などの提案できたり、ありとあらゆる節税方法を提案してくれる可能性が高いです。
したがって費用が高かったとしても、合計金額で抑えることができます。
また相続に関して、一番避けたいのが税務調査です。
国税庁の発表では、税務調査を受けた人の約80%に申告漏れがあり、不足分に加えて延滞税や加算税を支払っています。
税務調査が行われると平均して8割が適正に申告していないと指摘されてしまうことを考えると、適正に相続税の申告を行うのがいかに難しいのかが分かります。
費用が多少違ったとしても、実績のある相続の専門税理士に依頼し、できれば書類添付制度を利用してもらうと良いですね。