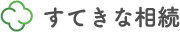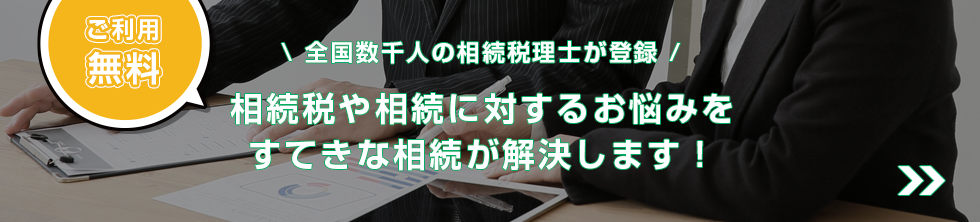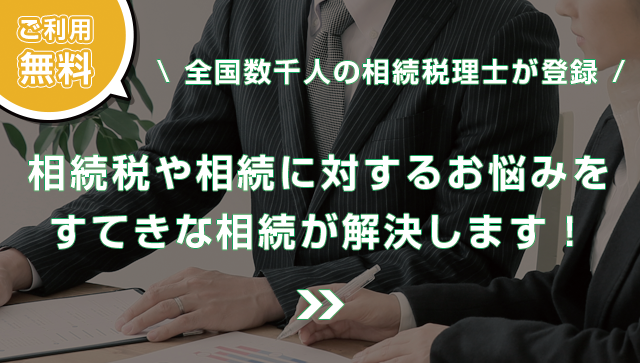2019年8月22日 木曜日
相続に備えて家族信託制度で財産管理!メリットと注意点とは?
みなさんは、家族信託という言葉をご存知ですか?
家族信託とは、民事信託とも言われ、家族の財産や生活を守る家族のための信託契約であり、相続対策として注目されています。
家族信託を活用して相続対策をすると、対象となる財産を自由に取り決めることができたり、資産継承まで可能となり、今まで相続対策としてできなかった対策が可能となります。
今回は、相続に備えて家族信託制度で財産管理を行うことについて、メリットと注意点についてご紹介します。
目次
家族信託制度とは?

家族信託制度とは、預貯金や不動産など財産を持っている方の財産管理の方法で、家族や親族など信頼できる方に信じて財産を託すことです。
特に子どもや配偶者のために利用したい場合、信託の組み立て方やしくみを多く選択できるので、個々のニーズに合わせて活用することができます。
第三者を入れないで親族や家庭内で財産の管理ができるため、高額な報酬が発生せず誰にでも手軽に利用できるのが特徴です。
信託財産の範囲は、金銭、金銭債権、有価証券、動産、知的財産権、土地・建物といった不動産などがあります。
家族信託の仕組み
家族信託は、委託者と受託者と受益者の3者によって成り立ちます。
委託者は自分の財産を託す人、受託者は財産を託される人、受益者は利益を取る人です。
対象となる財産をどんな目的で、どのようにして扱うのかという契約を交わします。
委託者と受託者が信託契約を結び、受託者が契約に基づき信託財産の処分・管理をおこないます。
そして、受益者に定期的に金銭などを交付するというのが、基本的な仕組みです。
ちなみに、委託者と受益者を同一人物とすることも可能です。
家族信託によって財産はどうなる?
家族信託を活用することで、受託者が財産管理を行えるようになります。
例えば委託者が認知症などを患い、判断能力が低下してしまった場合。
その状態で多額の財産を自ら管理することは難しく、詐欺被害などにあう可能性もありえます。
家族信託を活用すれば、受託者が各種財産の管理・処分を行うことが可能になります。委託者に代わって財産の使いみちを決定することが出来るので、結果的に財産を守ることに繋がります。
家族信託が必要とされる理由
これまでは、「生前に資産を管理する場合は委任」、「認知症などで判断能力が低下してしまった場合は成年後見」、「相続が発生した際の資産は遺言」、などそれぞれの状況に応じて制度を活用する必要がありました。
複数の制度を使うことで複雑になってしまいますし、各制度も万能ではないので、柔軟な財産管理を行うのは難しいものでした。
特に成年後見制度は、財産を持つ人に代わって財産管理を行う点では家族信託に近いのですが、専任された後見人に多くの負担がかかったり、後見監督人に対する報酬が発生したり、何よりも財産の活用方法を柔軟に決定しづらいというデメリットがありました。
一方、家族信託の仕組みならば、従来からの制度の問題を回避しながら、本人や家族の希望を実現できるような柔軟な設計と運用が可能となります。
また、家族信託のメリットは委託者の生前のみならず、相続が発生した後も効果を持続させることが可能です。
これらの理由から、成年後見制度や遺言の代替として、必要とされる場面が増えています。
家族信託を行うメリット
家族信託を行うメリットは、以下があげられます。
1.本人の判断能力や体調にかかわらず財産の管理処分ができる
2.成年後見制度の代わりに柔軟な財産管理ができる
3.遺言の代用と受遺者の財産管理を行える
4.思い通りの資産承継ができる
5.不動産の共有を回避できたり共有不動産のトラブルを未然に防ぐことができる
委託者が認知症や脳梗塞で判断できる能力が低下した場合であっても、財産は受託者が管理しているので、詐欺にあうことを防ぐことができるのがメリットです。
認知症対策として
現代の日本では、急速な高齢社会が進み認知症問題を抱えています。
内閣府の発表によると、65歳以上の認知症患者数が2012年は462万人と、高齢者の7人に1人でしたが、2025年には5人に1人となり、認知症患者数が700万人増加すると見込まれています。
財産を持っている方の認知症が認められると、資産の保護を目的に”資産の凍結”が行われます。
例えば本人が銀行窓口で預金払い戻しをしたり、不動産の売却などの行為ができなくなり、その他にも遺言書の作成や相続税の対策などが不可能となります。
資産が凍結されたまま相続が発生した場合、相続税対策を行った場合と比べて多くの相続税を支払わなければならない、といったことも起こりえます。
認知症への備えとして効果が期待されているのが家族信託です。
認知症対策として例えば、父を委託者、長男を受託者、父が受益者となる場合、
・何かあったとき父母への生活費を保護する
・老人ホームへの入所手続きをする
・不動産の管理を長男に託して信託契約を交わす
・長男は不動産の管理運営を行い、家賃収入から父母に対して毎月の送金と老人ホーム探しの手続きを行う。
・父が死亡した後は母への仕送りを行い続ける
受託者は、両親の認知症対策として資産が動かせなって困るような事態を未然に防ぐため、対策をしっかりと考えておくことが重要です。
成年後見制度に代わる財産管理
成年後見制度は家庭裁判所の監督のもと、きちんとした財産管理をおこなうことができる重要な制度です。
財産のある方が認知症などで判断能力を失ったときは、成年後見人を決める必要があります。
成年後見人になる方は、一般的にはほとんどが親族です。
ただし、未成年などは適格でなく、財産管理能力も欠けていますので、その場合は親族以外の第三者が成年後見人に選ばれるることもあります。
成年後見制度では、後見人選出を行うため家庭裁判所へ出向き、「後見開始の審判」の申立を行わなければなりません。
また、成年後見制度は、手続きの際に費用もかかりますし、家庭裁判所へ行ったり、事務作業など、本人が亡くなるまで後見人は職務が継続することになり負担がかかります。
家族にはなるべく多くの資産残したい方は、成年後見制度はできるだけ避けたいところです。
成年後見制度を利用してしまうと、積極的な資産活用や運用はできなくなりますので、相続税対策はできなくなります。
そのため、成年後見制度に代わる財産管理として注目されているのが家族信託です。
遺言のような機能を果たす
一般の人が信託以外の手法として、財産管理を利用できる仕組みを民事信託といいます。
民事信託の中でも、心を許した人々、つまり家族や親族に財産管理を任せることを家族信託と言います。
そのほかにも遺言代用信託、遺言信託、生前信託、福祉型信託などがあります。
障害者や高齢者のための財産管理の仕組みとして期待されていて、家族信託は、遺言のような機能を果たすしくみとして注目されています。
遺言にはできない財産相続方法がとれる
家族信託を利用することで、遺言では指定できないような財産相続方法をとることが可能になります。
遺言は一次相続のみを指定することができますが、家族信託であれば二次相続の内容を指定することも可能です。
また、財産を一括で相続させるのではなく、月◯万円ずつ分割で相続する、といった方法も可能となります。
ちなみに一次相続とは、両親の片方が亡くなり、子どもと配偶者が相続人になることであり、二次相続とは、一次相続後に残っていた親が亡くなったときの相続のことです。
二次相続の場合、相続の人数が減るので基礎控除額も減額となり、税率も変わります。
また、一次相続の際に使えた配偶者の税額軽減が使えないことで納める税金の額が高くなります。
そのため、二次相続にあらかじめ備えておくことは、相続税対策としても重要となります。
不動産の相続対策になる
家族信託では、委託者が認知症などになり判断能力が出来なくなった後でも、受託者の判断で不動産の売却や購入などが資産の運用ができます。
成年後見制度では、認知症などになった場合、本人の資産を維持するだけなので大きな違いがあります。
家族信託では、受託者が売買契約の当事者ですから、毎回委託者の承認はいりません。
ただ、受託者に対して認める行為の範囲を定めておくことがとても重要です。
家族信託では、
第一受益者が死亡→第二受益者
第二受益者が死亡→第三受益者
このように受益権の承継先を設定しておくことができます。
遺言は、相続財産の引継ぎは次世代までとなりますが、家族信託を活用すれば、次世代、その次の世代へと繋げていくことができます。
ただし、信託開始から30年が経過してからは、受益権の承継が認められるのは1回のみです。その受益者が死亡したら、信託は終了となります。
信託契約終了の際に、最終的に残っている財産の所属先を決めておくことも可能です。
このように、何世代にもわたって財産の継承方法を決定することが出来るため、遺言よりも将来確実に財産を継承していけるでしょう。
信託を開始すると、不動産の登記上の所有者名義は委託者から受託者へと移転します。
信託登記の際の登録免除税は減少し、受託者には不動産取得税は課税されません。
また、それにより特に利益が生じず、受託者に贈与税が課税されたり、委託者に譲渡所得税が課税されることもありません。
また、信託財産に入っておけば、親が亡くなる前に売却ができるので覚えておくと良いですね。
家族信託の注意点とは?

家族信託でのメリットはお伝えしてきましたが、メリットだけではありません。
家族信託の注意点をご紹介します。
受託者の選定でトラブルの可能性
家族に託すことになった場合、誰を受託者にするかで揉めることがあります。
元々財産の継承者であれば、誰も文句は言わないですが、継承者が複数いる場合や、逆に継承者に相当する人がいない場合は、受託者の選定でトラブルの可能性があります。
また、家族信託を利用して受託者を決めたとしても、身体的な保護を管理する権限、つまり身上監護権はありません。
受託者が勝手な行動に走る可能性
家族信託を利用して二次相続まで決めた場合、本人は安心かもしれませんが、受託者が勝手な行動に走る可能性もあります。
相続のトラブルを回避するために利用したのに、かえってトラブルを起こしてしまうこともあるので注意が必要です。
必ず節税になるわけではない
「家族信託は節税に繋がる」という言説もあるようですが、家族信託それ自体には、相続税や贈与税の負担を軽くする効果はありません。
あくまでも委託者に代わって財産を管理するものであり、その管理方法次第では節税に繋がる可能性はあります。
しかし、家族信託を組んだだけで即座に節税になるわけではないので、その点は誤解のないよう、注意が必要です。
資産の扱いに制限がかかってしまう
家族信託の機能には資産承継の指定があります。
後継ぎ遺贈型受益者連続信託で、一次相続、二次相続、それ以降の資産継承を自分で決めることができる機能があります。
複雑な家庭などの場合、事業継承や資産承継において大きな効果を持つことになるでしょう。
一方、次世代それ以降の長期にわたって資産の扱いに制限がかかってしまいます。
かえって不測の事態を誘発する可能性もありますので、20年、30年先を考えて家族信託の設計を行うことが重要です。
相談可能先が少ない、事例が少ない
家族信託制度は歴史が浅く、専門家はまだまだ少なく事例も少ないため、正確な情報を提供してもらえる専門家になかなか巡り会えない可能性もあります。
とはいえ、自分たちだけで家族信託を実行するのはかなりのリスクです。信頼できる専門家を見つけて十分に相談した上で、制度を活用していくことをおすすめします。
ただし、そういった専門家は数が限られるうえ、長期的なサポートを伴う家族信託の相談は、時間と知識が求められるものとなり、結果的に報酬が高額となる可能性があります。この点にも注意しておくべきです。
家族信託の相談はどこにすればいい?
家族信託の相談はどこにすればいいのでしょうか?
家族信託を失敗しないためには、相談先として一般的には弁護士、司法書士、税理士などの士業へ相談するようにしましょう。
ただし、弁護士や司法書士の資格を持っていたとしても、必ず家族信託に詳しいというわけではありません。
まだ新しい仕組みのため、家族信託の実務経験が豊富な専門家を選ぶようにしましょう。
また家族信託を相談する際には、例えば司法書士に相談するだけでなく税理士にもチェックしてもらうなど必要に応じて、その専門家に相談することがおすすめです。
では手続きをする前に一体どのようなポイントを押さえて選べば良いのでしょうか。
・家族信託専門の取り扱い件数が多い
・相続を専門としていて実務経験が多い
・信託登記・成年後見・遺言など幅広く相続に関する相談ができる
このように過去の信託契約の件数やコーディネートの実績など、指標となるようなものを選ぶポイントにしましょう。
まとめ
今回は、家族信託制度の概要と、メリットや注意点についてご紹介してきました。
今までは成年後見制度が主に活用されていましたが、最近では、家族信託を利用する方も少しずつ増えてきています。
家族信託のメリットと注意点をしっかりと理解した上で活用してきましょう。