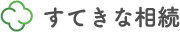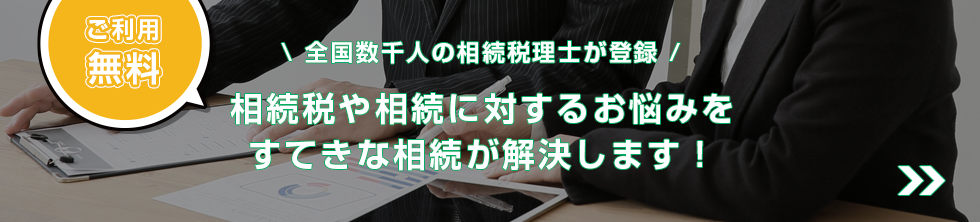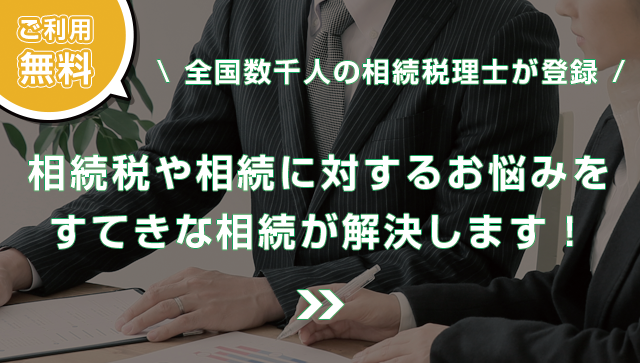2019年6月22日 土曜日
未支給年金は相続の対象になる?相続税の対象にはなるのか?
日本全国において、「年金だけでは暮らせない」「年金をもらえるかわからない」等の懸念のため、人生100歳時代と言われる時代になりました。
年金の仕組みは複雑で、完全に理解できている方は多いとは言えません。
さらに、まだ年金が支給されずに亡くなった方の未払い年金は、相続において非常に複雑です。
この記事では、未支給年金を軸に、年金の種類と相続について詳しく解説していきます。
目次
被相続人の年金は死亡後に受け取れる?
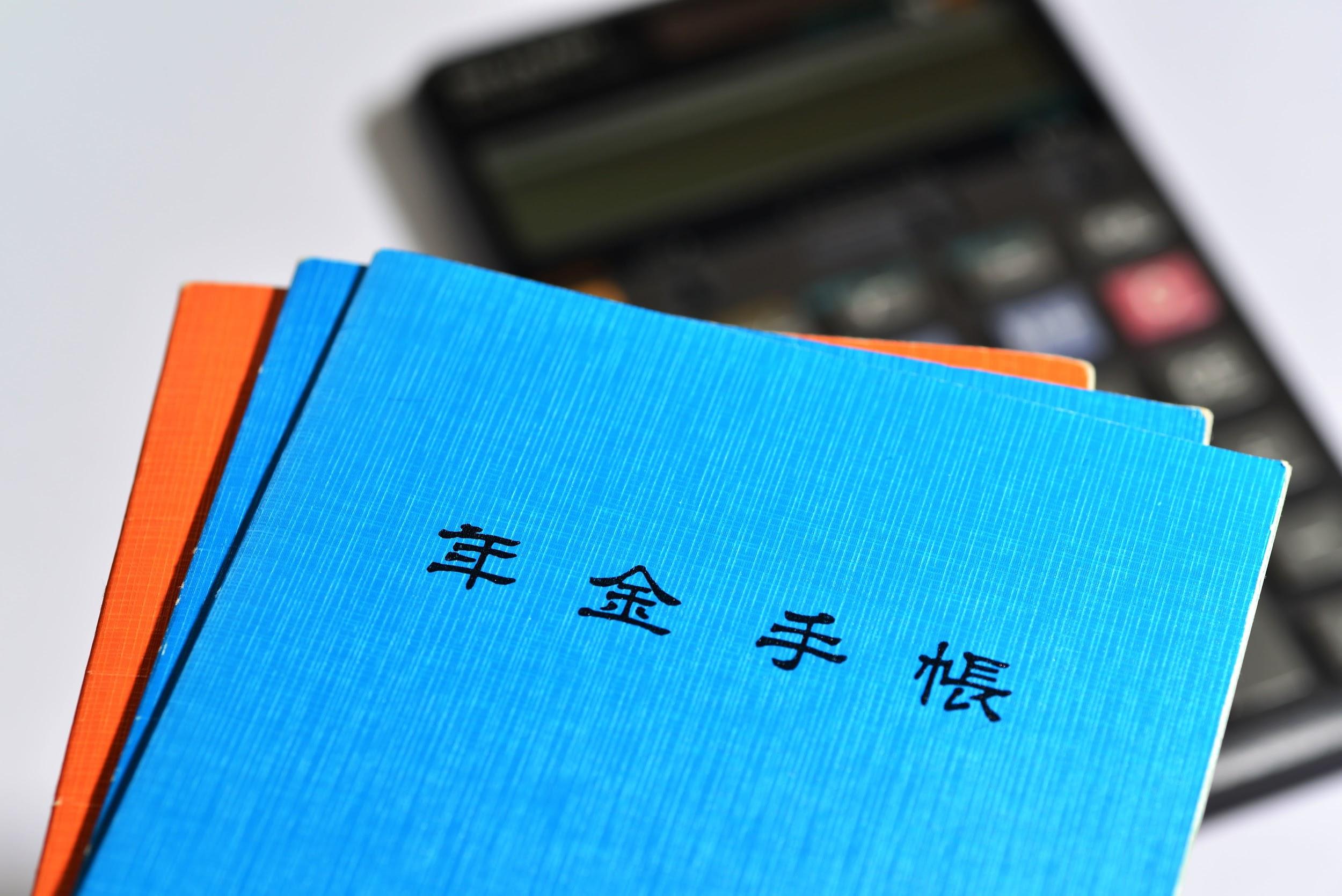
ここでは、「未支給年金」「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「寡婦年金」「死亡一時金」等の被相続人が亡くなった後に受け取れる5つの年金について解説していきます。
年金を受けている方が亡くなったら、まずは年金事務所または年金相談センターに「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出しなければなりません。
厚生年金は死亡日から10日以内、国民年金は死亡日から14日以内という提出期限がそれぞれ定められています。
日本年金機構にマイナンバーを登録している場合は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出は不要となります。
未支給年金とは
未支給年金とは、故人が年金を受給する前に亡くなってしまった際の、未支給分の年金のことを言います。
未支給年金は、「年金を受給する前」や「年金を請求しないうちに」亡くなってしまった場合に、遺族が請求することができます。
年金は、2ヵ月に1度、2ヵ月分を偶数月に振り込まれます。
年金は通常「後払い」のため、年金を受給していた場合は必ず未支給年金が発生します。
従って、遺族が未支給年金を受給する場合は、遺族が各年金の期限内に請求手続きを行う必要があります。
未支給年金を受け取れる遺族
年金を受けている方が亡くなった際に、受け取りが完了していない年金や、亡くなった日付以降に振り込んだ年金のうち、亡くなった月の分までの年金は、未支給年金として、故人と生計を一にしていた遺族が受け取ることができます。
優先順位の高い方から、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等内の親族、となります。
亡くなった方に一定の遺族がいる場合は、「遺族基礎年金」や「遺族厚生年金」の受給対象となります。
遺族年金とは
遺族年金とは、国民年金法と厚生年金保険法に基づいて、被保険者が亡くなった際に、遺族が受給できる日本における公的年金のことを言います。
現在は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」が遺族年金として活用できます。
一家の大黒柱を失った場合に家族の暮らしを支えるのが、遺族年金の役割です。
従来、遺族年金を受給できる人は、「子がいる妻」「子」に限られており、夫は受給の対象外でしたが、現在は「子がいる妻」から「配偶者」に変更され、父子家庭も対象となりました。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いは、「支給対象者の範囲」「支給期間」「支給金額」の3つです。
遺族基礎年金
遺族基礎年金の「支給対象者」は、国民年金加入中の方が亡くなった際、その方による生計維持関係にあった「18歳未満の子(障害の状態にある場合は20歳未満)がいる配偶者」または「子」と定められています。
「支給期間」は、配偶者は子が18歳まで(障害のある場合は20歳まで)、子は18歳まで(障害のある場合は20歳まで)というように 支給期間に制限があります。
遺族基礎年金の「支給金額」は「定額」で、子供の人数によって基本額に加算されます。
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、被保険者中、あるいは被保険者が亡くなった際に、故人による生計維持関係にあった方々が「支給対象者」となります。
従って、「妻、子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない方、または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の方)、55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給開始だが、夫が遺族基礎年金を受給している場合、遺族厚生年金も合わせて受給することが可能)」等の方々が当てはまります。
また、遺族厚生年金の「支給期間」原則として、期間制限がありません。
例外として、30歳未満の子供がいない妻の場合に限り、5年間のみの支給期間と定められています。
さらに、「支給金額」においても、遺族厚生年金は「報酬比例」となるため、日本年金機構で定められた式を元に算出した金額となります。
従って、遺族厚生年金の方が、「支給対象者の範囲」「支給期間」「支給金額」全てにおいて、柔軟性があると言えるでしょう。
寡婦年金
寡婦年金とは、受給対象者が「妻のみ」と限定されているため、男女格差のある年金制度と言えます。
仮に妻に先立たれたとしても、残された夫は寡婦には当てはまらないため、年金が支給されることはありません。
さらに、受給対象者も限定されており、寡婦年金は、主に「自営業者の妻」向けの制度となります。
寡婦年金を受給条件は、以下の5つがあります。
①夫が10年以上国民年金を納付していること
自営業を営む夫が、第一号被保険者(自営業等)として、10年以上保険料を納付していることが第一条件です。
さらに、その夫と10年以上の婚姻関係がある、または内縁の妻であることが寡婦年金の受給対象として定められています。
他には、
②夫が障害基礎年金の受給権者に当てはまらず、老齢年金の受給歴もないこと
③夫によって夫婦の生計維持が為されていたこと
④夫の死亡時の年齢が65歳未満であること
⑤夫の死亡後の5年以内に寡婦年金を請求していること
があげられます。
寡婦年金の支給期間は、60歳から65歳までの5年間という短い期間のため、妻が60歳になる前に被保険者である夫を亡くした場合は、死亡一時金を受給するという選択肢もあります。
寡婦年金の支給金額は、夫が本来受給するはずだった老齢年金の4分の3に値する金額を受給できます。
寡婦年金は、子供がいない妻というイメージがありますが、原則として、「夫が厚生年金に加入していない妻」が条件とされています。
夫が自営業者ではなく会社に勤務しており、子供がいない場合は、遺族厚生年金をもらうことができます。
ただし、遺族厚生年金と寡婦年金を両方受給することは認められていません。
とはいえ、寡婦も遺族厚生年金を受給することができます。
その場合、中高齢寡婦加算の活用を推奨します。
中高齢寡婦加算とは、40歳から65歳までの25年間の期間、遺族基礎年金の4分の3に値する金額を受給できます。
死亡一時金
死亡一時金とは、家族が亡くなった際に一時的に受けられる制度です。
死亡一時金は、保険料を納めた月数に応じて支給されるため、12万円から32万円まで受け取ることができます。
死亡一時金の受給対象者は、優先度が高い順に、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹となります。
死亡一時金の受給に際して、以下の5つの条件を満たす必要があります。
①故人が、第一号被保険者(自営業等)として、36ヵ月保険料を納めていたこと
②寡婦年金と遺族基礎年金のどちらの支給条件も満たしていないこと
③障害基礎年金や老齢基礎年金を受け取っていないこと
④亡くなった方と生計を一にしていたこと
⑤請求期限である2年以内に請求すること
寡婦年金と死亡一時金では、前者の方が、圧倒的に受給額が多いため、選ぶとしたら「寡婦年金」が推奨されます。
しかし、本来は65歳以降に受給できる老齢基礎年金を、65歳になる前に繰り上げ受給していた場合、寡婦年金と合わせて受給することは認められていません。
従って、この場合における妻は、65歳になっても寡婦年金の制度は適用されません。
そのような場合は、死亡一時金を受給することが推奨されています。
老齢基礎年金を65歳より前に受給していないのであれば、老齢基礎年金が受給されるまで、寡婦年金を受給することが認められています。
公的年金と私的年金では相続税の対象かが異なる
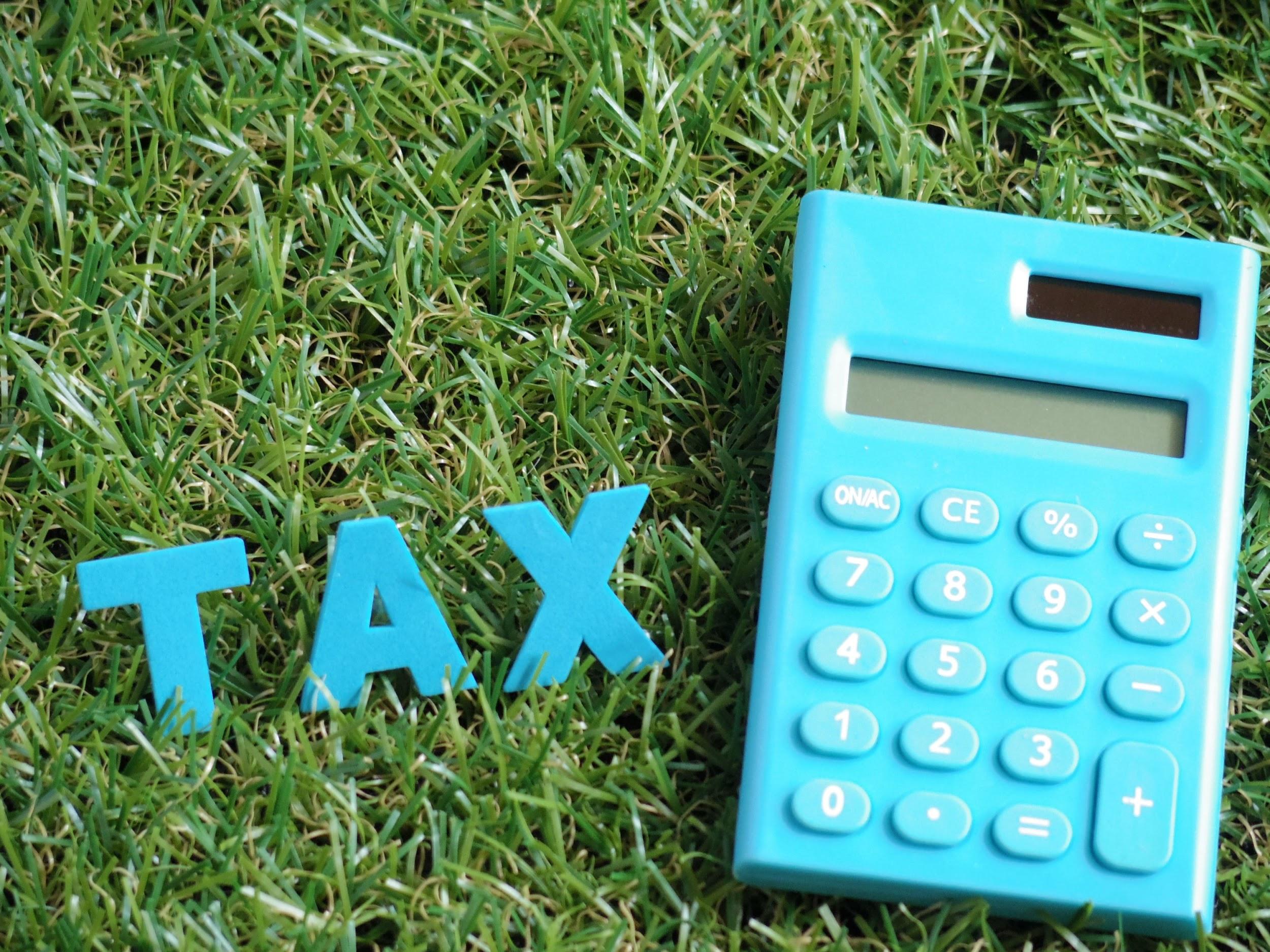
ここでは、公的年金と私的年金の相続税の対象について解説します。
公的年金の場合
公的年金とは、国が運営する年金全体を指します。
公的年金は、現在は「国民年金」と「厚生年金」、「共済年金」の3種類があります。
国民年金は全ての国民を対象としている制度、厚生年金は会社に勤務している方が国民年金と合わせて加入する制度、共済年金は、公務員・私立学校教職員等に向けた制度です。
「国民年金」は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の全ての人が加入を義務付けられており、老齢・障害・死亡によって、「基礎年金」の受給が可能になります。
国民年金は、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類があり、各制度で対象者が異なります。
「第1号被保険者」は、学生、フリーター、無職、農業等に従事する方が対象です。
「第2号被保険者」は、厚生年金保険が適用されている事業所に勤務する方であれば、65歳以上で老齢年金を受給する人を除き、自動的に国民保険に加入されます。
「第3号被保険者」は、第2号被保険者で20歳以上60歳未満の配偶者が対象です。
ただし、年間収入が130万円以上を超えており、健康保険の扶養となれない方は、第1号保険者となります。
「厚生年金」は、厚生年金保険に加入している方が、国民年金に加入する第2号被保険者に分類され、国民年金の給付である「基礎年金」と「厚生年金」の両方を受給することになります。
「共済年金」は、共済(組合)制度として、国家公務員や地方公務員、教員等として常時勤務する方が対象です。
共済組合には、「短期給付」と「長期給付」があり、前者は、健康保険と同様の給付を行い、後者は、年金給付と同様の給付を行います。
遺族が未支給の公的年金を請求した場合、相続税は発生しません。
なぜなら、遺族は、当該未支給の年金を「自己の固有権利」として請求するためです。
この場合の相続は、被保険者の収入によって生活維持を可能としていた遺族の生活保障を目的としています。
従って、その遺族の一時所得となり、相続税はかかりません。
私的年金の場合
私的年金とは、公的年金の上乗せの給付を保障する制度であり、所謂「個人年金保険」を指します。
例として、国民年金基金、確定拠出年金、確定給付企業年金、民間の保険会社等があげられます。
私的年金の役割は、老後の生活をより豊かにすることです。
充実したセカンドライフを送る上で、私的年金は非常に重要であり、企業や個人は、多様な制度の中から、自社・自身のニーズに合わせてプランを組むことができます。
私的年金は、「確定給付企業年金制度(DB)」と「確定拠出年金制度(DC)」の2種類の年金制度に分けられます。
確定給付企業年金制度(DB)は、加入した期間に基づいて予め給付額が定められています。
労使の合意によって、比較的柔軟な制度設計ができ、受給権が保護されているというメリットがあります。
確定拠出年金制度(DC)は、拠出した掛金額とその運用収益との合計額を基に給付額を決定します。
加入者自らが運用を行い、老後の生活設計を立てる必要があります。
確定給付企業年金制度(DB)の企業年金を適用することが難しい中小企業の従業員や自営業者等のニーズに応え、離職や転職にも対応しやすいことから、年々需要が拡大しています。
入院保険、医療保険、介護保険等は、本来生前に受け取るべきものを遅れて受け取ったことになるため、受け取った額は相続財産という扱いになります。
従って、みなし相続財産(相続遺産とみなされる財産)ではないため、課税の対象となります。
従って、私的年金を受け取る際には、原則として相続税が発生します。
未支給年金の有無を確認するには?

年金を受給していた方が亡くなった際は、年金事務所に未支払給年金の有無を確認しましょう。
正確に言えば、「未支払給年金の金額」を確認することとなります。
公的年金は、「請求しなければ受給できない」「後払い」という特徴から、必ず未支払給年金が発生します。
「請求しなければ受給できない」ということは、65歳で受給権が発生しているのにもかかわらず、請求手続きをしないまま67歳で亡くなれば、2年間分の未支給年金が発生します。
請求しないまま亡くなるケースはあまり多いとは言えませんが、配偶者の年金の請求の有無に心当たりがある方は、念のため確認した方が良いでしょう。
公的年金は、原則として年に6回偶数月に2ヵ月分ずつ支払われます。
それも、4月分は、2月分と3月分を合わせた「後払い」です。
仮に、4月に亡くなったとしたら、4月まで年金を受給する権利があるにもかかわらず、支払われていないことになります。
従って、2月分と3月分が未支給年金となります。
未支給年金は、「老齢年金」だけでなく、「障害年金」や「遺族年金」においても発生します。
いずれにせよ、家族が亡くなった際は、「年金受給権者死亡届(報告書)」を年金事務所または年金相談センターに速やかに提出するとともに、未支給年金の確認を行いましょう。
私的年金よりも生命保険の方がお得?

私的年金の未支給年金を受け取る際は、相続税が課せられてしまいます。
しかし、非課税で相続できる保険が1つだけあります。
それは、生命保険です。
生命保険の「死亡保険金(終身保険)」は、非課税枠となります。
私的年金と生命保険の違いは、「死亡保障の大きさ」です。
私的年金は、支払った保険料相当額が受け取れるのみのため、将来年金を受け取る際の積立という捉え方になります。
一方、生命保険は、被保険者が亡くなった際に死亡保険金を受け取ることができるため、支払う保険料よりも大きな保障を受けられます。
従って、ご自身の死後にご家族へ多くの財産を遺したいのであれば、私的年金よりも生命保険の方がお得と言えます。
まとめ

この記事では、未支給年金の基本情報や、公的年金と私的年金によって相続税の対象が異なることを解説しました。
公的年金は原則として非課税、私的年金は課税対象となりますが、「生命保険」のみは非課税枠になります。
ご自身の状況や法定相続人の人数などによっても、どれがベストの選択になるかは変わって来ます。
これを機に、お金の専門家である税理士と一緒に、ご自身やご家族の年金状況を確認し、どの選択肢を家族に遺すのかを相談してみてはいかがでしょうか。