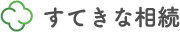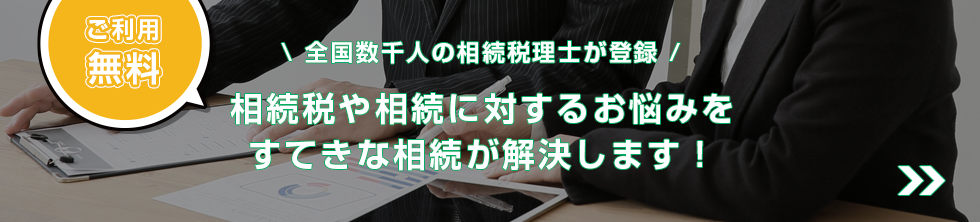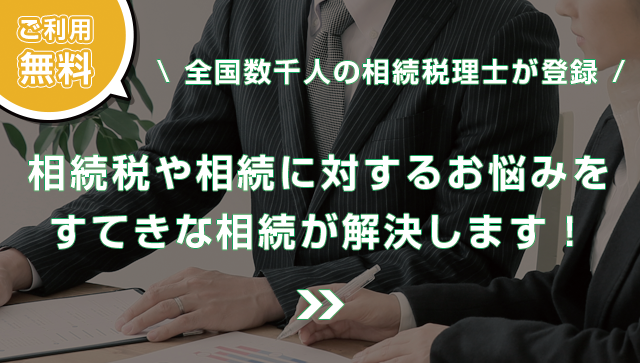2019年8月11日 日曜日
遺産分割を禁止する理由、方法、その効果とは?
相続の際に気になることといえば、「遺産分割」についてではないでしょうか?
遺産分割とは、遺言書が無く、相続人が複数人の場合、相続開始後に相続人全員で被相続人の遺産をどのように分配するか決める話し合い、遺産分割協議により決める一連の行動のことを指します。
では「遺産分割の禁止」という言葉はご存知でしょうか?
本稿では「遺産分割の禁止」の概要やその方法、またどのような場合に行うのかという点や、知っておくべきことについてご紹介していきます。
目次
遺産分割の禁止とは?

遺産の分割は、相続開始後、原則としていつでも行うことができます。
遺産分割の協議は書面でも対面でもでき、話し合いがまとまり相続人全員が合意をすると、協議は完了となります。
しかし、その時の状況や必要な条件が揃えば、遺産分割を禁止することもできるのです。
遺産分割の禁止は、一定期間、遺産の分割を停止する方が適切だと判断された場合に行われます。
では、遺産の分割を停止することで、どのような効果があるのか、またどのような条件が必要なのかを具体的に見てみましょう。
遺産分割の禁止による効果
遺産分割の禁止とは、遺産の分配について相続人間で紛争が起こりそうだと予測される場合や、紛争が起こってしまった場合に、遺産の分割を停止することができる制度のことです。
一定期間遺産分割を停止することが可能となるため、その期間に相続人間で遺産の分割について話し合いを行うことが可能です。
遺産分割の禁止は、包括承継人に対してだけではなく、特定された一部のみ承継できる特定承継人に対しても効果があります。
不動産の場合において、遺産分割の禁止を第三者に主張するためには、登記が必要になりますので注意が必要です。
また、遺産について相続税がかかる場合、相続開始後10か月以内に相続人全員が申告し納税する必要があります。
申告期限までに相続税の申請ができなかった場合、減税の特例が受けられないなどのデメリットがありますが、遺産の分配が未実施であることについて、やむを得ない、と税務署長の承認を得られれば、減税の特例を受けることができます。
その場合、相続税の申告が遅れたことによるペナルティの追加納税も発生しません。
遺産分割の禁止の条件
遺産分割の禁止を実行することができる期間は、民法で”5年を超えない期間”とされています。
5年以内であれば、2年でも3年でもその期間を定めることが可能ですが、「5年を超えない期間」とされているのは、長期間、遺産が共有状態であることを防ぐ目的があります。
民法では、遺産の単独所有が望ましいという考えがあるため、民法の性質上期間の上限が定められているようです。
遺産分割の禁止は、「遺言による方法」「家庭裁判所による方法」「相続人間の合意による方法」などがありますが、どの方法においても期間の上限は同じ5年を超えない期間です。
各方法についての詳細は、後ほどご紹介します。
なお、遺言による方法では物理的に難しいためできませんが、相続人間が合意を得たうえで停止する方法であれば、この期間を更新することも可能です。
更新後の期間も5年を超えない期間とされているため、実質5年毎の更新ができることになります。
遺産分割の禁止の必要性とは?
では、遺産分割を禁止するのはどのようなケースになるのでしょうか?
シチュエーション別に3つご紹介します。
①相続人に未成年の若年者が含まれる場合
若年者は、判断力が未熟なため、話し合いによる遺産分割において不利になる可能性があります。
そのため、判断力が十分に養われてから改めて遺産分割を開始できるよう、一時的にストップさせることができるのです。
早くにお子さんを亡くし、未成年のお孫さんに事業を引き継ぐケースなどはこれにあたります。
未成年者が叔父叔母と遺産分割の交渉を行いながら、事業を取り仕切ることは大きな負担になることが予想されますね。
このようにリスクが高いと判断される場合には、遺言を使って遺産分割の禁止を行うことで、若年者が成熟するまで期間をあけ、相続の負担を軽減することができます。
②遺産の範囲について民事訴訟が提起されている場合
遺産分割を行う資産について、民事訴訟が提起されている場合は、問題の解決を待って遺産の分割を行うべきです。
そのため遺産分割の禁止を行い、問題が解決されるまで分配を停止する場合があります。
被相続人の遺産の範囲が明瞭でない場合などは、民事訴訟で解決することになります。
生前の財産状況が不明瞭な場合などはこのケースにあたりますので、覚えておくと良いでしょう。
③相続人が確定していない場合
何らかの理由で、相続人が確定していない場合、また相続人の関係性が複雑な場合は、相続発生直後から遺産分割を進めていると、相続紛争が起こるリスクが高くなってしまいます。
相続紛争のリスクを避けるためにも、相続人が確定するのを待つ必要性があります。
例えば、相続発生後に、家族ですら知らない嫡出子の存在が明らかになった場合など、複雑な相続関係になっている場合です。
相続人の確定に時間を要する場合はこのケースにあたるため、確定するまで遺産の分割を停止することが妥当です。
このように、相続紛争のリスクが高い場合に、遺産分割の禁止を行うことで、相続紛争のリスクや紛争の深刻化を未然に防ぐことができるのです。
遺産分割の禁止を行う方法とは?

遺産分割の禁止は様々なケースで必要になってきますが、実際に遺産分割の禁止は、どのような方法で行うのでしょうか。
停止する方法は、主に「遺言による禁止」「家庭裁判所による禁止」「相続人全員の合意による禁止」「相続人の合意に至らない場合」の4つがあります。
以下より順番にご紹介していきましょう。
遺言による禁止
被相続人が生前に禁止することができるのが、遺言に記載する方法です。
相続直後に遺産分割をすることが望ましくないと考える場合は、遺言に必要な内容と5年を超えない期間を記すことで、遺産の分配を停止することができます。
ちなみに、被相続人が遺産分割の禁止を実行したいと思う場合に、取れる手段は遺言以外にはありません。
生前に口頭など別の方法で相続人に伝えたとしても、効力はありませんので、必要な場合は、必ず遺言に記載するようにしましょう。
ただし、遺言に書かれていたとしても、相続人間の話し合いで遺産の分割ができる場合があります。
以下の場合は注意が必要です。
・遺産分割の禁止が著しく不相応な場合
・特定の相続人の利益のために禁止されており、その特定相続人が同意する場合
・禁止の目的が相続人全員の利益を考慮してうえだったが、すべての相続人が分割しても良いと合意した場合
家庭裁判所による禁止
「特別の事由」があれば、家庭裁判所が遺産分割の禁止をすることができます。
どのような場合に適用されるのか例を挙げてみてみましょう。
特別の事由の例
◆遺産の分割の前提に問題がある、紛争が起きている
・相続財産の範囲が定まっていない
・相続人が明確になっていない
このように、遺産を分割するための前提について紛争がある場合は、遺産の分割手続きを直ちに行うと相続紛争が深刻化するリスクが高まってしまいます。
すでに相続紛争があり、民事訴訟が進行中の場合は、訴訟にて相続財産や相続人が明確になるのを待ってから分配を始めることになります。
◆遺産の過半を占める不動産で争いごとがある
・不動産の境界を隣人と争っている、民事訴訟中である
このような場合は、分割を進めても適切な判断ができません。
正しく進められるよう、争いの解決を待って分割を実行することが可能です。
◆事業継続のための資産の分散を避ける
・直ちに遺産を分割した場合、事業継続が困難である、もしくはできない
事業用不動産を、遺産の分割のために売却されては、事業の承継者が困ってしまいます。
そのような場合は、方針が決定するまで遺産の分割を停止することができます。
◆株式など市場の影響を受ける資産の換価分割を行う場合で、著しく価額が低迷している
・直ちに換価した場合、相続人に大きな損失が出てしまう
換価分割とは、遺産を売却後、相続人で金銭の分割を行う方法です。
著しく相続人に不利な価額の場合は、市場の回復を待つため、遺産の分割を停止することができます。
このように、直ちに遺産を分割することが好ましくない場合や、相続人の不利益になるような場合には分割を停止することができるのです。
相続人全員の合意による禁止
相続人の意思によって禁止する方法もあります。
この場合は全員が合意すれば、一定期間遺産の分割を停止することが可能です。
相続人間で合意をしたことや、その内容については、後々紛争にならないように、書面に残しておくと良いでしょう。
相続人の合意に至らない場合
相続人間で遺産分割の禁止について話し合いがまとまることが望ましいですが、どうしても合意が得られない場合には家庭裁判所にその調停の申立を行う方法があります。
協議がまとまらない場合や、共同相続人が入院中で、退院まで話し合いが難しい場合など、特別な理由があれば調停という方法を取れるということを覚えておきましょう。
遺産分割の禁止について、その他の知っておくべきこと
相続の紛争リスクや深刻化を避けるために設けられている遺産分割の禁止ですが、概要や方法の他に知っておいたほうが良いことが2つあります。
それは「禁止の範囲を定められること」と「遺言書の記載方法」です。
以下より詳しくご紹介しましょう。
遺産分割の禁止は範囲を定められる
遺産分割の禁止は、遺産の全体ではなく、一部の遺産のみなど、禁止の範囲を定めることが可能です。
問題のある、もしくは問題が起こる可能性が高い特定財産のみ分割することを禁止し、それ以外の遺産については分割を進めることができます。
特定財産以外については問題が起きていない場合も多いため、一部の資産のみ分割を停止することで財産の共有部分を減らすことができるよう、このような対応が取れられています。
遺言にはどう記載するか
遺産の分割を遺言にて禁止する場合は、以下のことを記載します。
・禁止期間
・禁止期間終了後の自身の意向
・資産の範囲
期間については先にもご説明しましたが、5年を超えない期間で、任意の期間を指定することができますので、必要な期間を指定します。
禁止がとけた後の遺産分割の協議方法、また分割について意向が決まっている場合は、その後どのようにしたいかについても記載しておきます。
遺言では、5年毎の禁止の更新ができないため、禁止期間終了後の自身の意向について、はっきりと記載しておくと、相続人も分かりやすいでしょう。
また、遺産の分割を一定期間しない資産の範囲(遺産のすべてなのか、一部なのか)が分かるように記載します。
例えば、事業を行っている場合、資産が分散して困る範囲が明確な場合は、事業用不動産のみとすることもできます。
ただし、不動産の場合は、禁止期間にも不動産収入が入ることがありますので、その収入をどうしたいかの意向も加えて記載しておくと、相続人も取り扱いが分かりやすくなります。
記載の際には、特定の相続人の利益にならないような配慮も必要です。
相続のトラブルを避けるためにも、生前に遺産分割の禁止を遺言で残しておくと安心ですね。
遺言が無効になると、遺言による遺産分割の禁止も無効になるので、遺言を有効なものにするため公正証書遺言にしておく方が無効になるリスクが低くなります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
遺産分割の禁止は相続発生後の紛争リスクを低減させることができる手段であり、また相続トラブルの深刻化を避けることができる手段でもあります。
遺産の分割について、相続人間でなかなか話し合いがまとまらない場合は、このような方法があることを相続人間で共有し、時間をかけて協議するという選択をしても良いでしょう。
また、遺産の分割について遺言を残したいけれど、相続発生直後に遺産分割を行うことが難しいと考えている場合は、一度遺言による禁止の方法も検討してみても良いかもしれません。
相続は突然発生します。
相続人が複雑な場合や、資産が不明瞭な場合は、トラブルが起こることもめずらしくありません。
遺産の分割で相続人が困りそうな場合や、実際に困っている場合は、選択肢のひとつとして、分割の禁止を検討してみてはいかがでしょうか。