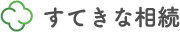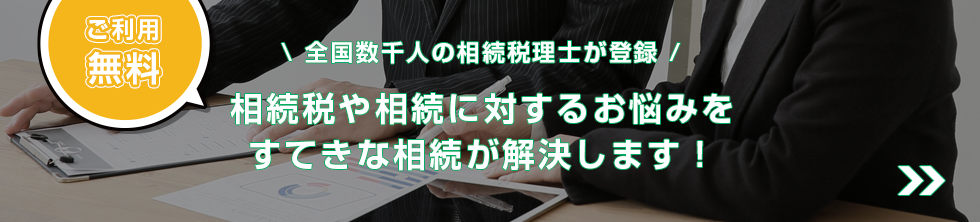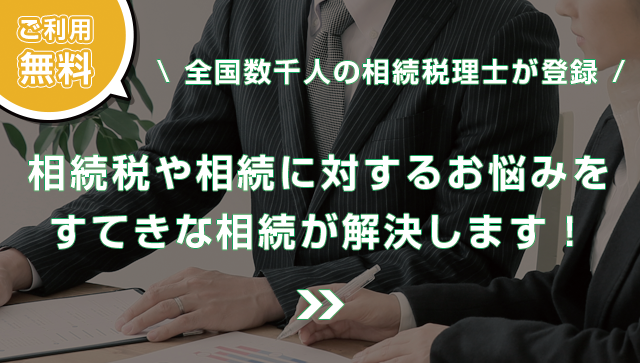2019年2月20日 水曜日
相続時に遺留分がある場合の請求方法や注意点
いわゆる法定相続割合については知識があるものの、遺留分についてはそうではないという人は意外に多いようです。
この遺留分という制度は、遺産の取り分に対する各法定相続人の最低限の権利を保証するものです。
しかし、このことを知らずに遺留分を侵害した遺言を書いたために、相続発生後に遺族間でトラブルになってしまったケース、あるいは遺留分が侵害されているにもかかわらず遺留分の概念を知らないまま権利を行使できる時効を迎え、結果的に遺産に対して本来取得できるべき権利を喪失してしまっていたというケースは数多くあるのです。
本コンテンツでは、遺産分割に際して重要なポイントとなる遺留分に関する基礎知識をご紹介します。
目次
遺留分とは

民法第900条では法定相続人の原則的な遺産の取り分について「法定相続割合」を定めていますが、さらに各法定相続人の最低限の取り分として「遺留分」を定めています。
遺留分が設けられている背景のひとつは、被相続人の法定相続人である遺族の生活を守るためです。
生前に被相続人(亡くなった人)が自身の遺産の相続人および相続割合を指定する方法として、遺言があります。
この遺言で指定した相続割合は、民法で定められた法定相続割合に優先して強い法的実効力を持ちます。
しかし、たとえ遺言であろうと遺留分の規定に反して遺産分割割合を指定することはできないようになっています。
参考:民法第902条
「被相続人は、前二条(法定相続人および代襲相続人の相続分)の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない」
このように民法では、被相続人の配偶者や子どもなど、被相続人の収入や財産を頼りに生活していたと推定される人には、遺留分として最低限相続することができる財産の割合および請求権を保証しています。
このため、例えば被相続人が、配偶者や小さい子どもがいるにも拘らず遺言で全財産を愛人などの家族に関係ない第三者に譲るような指定を行い、遺された家族の生活に大きな支障が出てしまう、といったことを防ぐことができるのです。
遺留分の対象財産の請求

対象となる財産
遺留分は、基本的に被相続人の財産すべてが対象となります。
言い換えると、遺産として扱われない財産は遺留分の対象となりません。
例えば、被相続人が契約者もしくは被保険者で、保険金受取人を相続人とする生命保険の死亡保険金は、保険金受取人の固有財産とされていますので、遺留分には原則として含まれません。
また、祖父母が信託銀行に孫の教育資金として1,500万円を限度に金銭を信託する「教育資金贈与信託」についても、孫の親―つまり祖父母の子が生きている限りは、孫は祖父母の相続人ではありませんので、これについても原則として遺留分の対象にはなりません。
なお、遺留分は特別受益を考慮する必要があります。
特別受益とは、被相続人の生前に受けた生活資金の援助や住宅などの贈与というように、他の相続人と比較すると特別な利益の供与のことです。
被相続人から特定の相続人に特別受益がなされていると、それがなされていない相続人との間で、財産の分与の観点から不公平が生じます。
したがって、他の共同相続人との公平性を確保するために、遺産の前受け分として特別受益が考慮されるのです。
この特別受益は相続財産ひいては遺留分の算定に加算されるものとされています。
参考:民法第903条
「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする」
仮に、被相続人が生前に「特別受益分は相続財産に考慮しない(持ち戻し免除)」の意向を示していたとしても、原則としてその意向は反映されず、特別受益分は遺留分に加算されます。
(※ただし民法改正によって、相続開始前10年以内の贈与については、持ち戻しが認められる可能性が出ています。)
なお、先述した生命保険金の死亡保険金については、当該死亡保険金の相続財産に占める割合次第で、特別受益とみなされることがあります。
同様に、教育資金贈与信託についても、『孫の親つまり祖父母の子が死亡しており、孫が祖父母の代襲相続人となる場合』あるいは『孫への教育資金贈与としていても実体的には子への贈与と認定された場合』などは特別受益とみなされる可能性があります。
請求方法
遺留分を侵害された相続人は、遺留分権利者として民法第1031条の規定に基づき、遺留分権利者として侵害した他の相続人に対して「遺留分侵害請求(改正民法の施行後は遺留分侵害額請求)」をする権利が認められています。
参考:民法第1031条
「遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条(相続開始1年前の贈与の規定)に規定する贈与の減殺を請求することができる」
なお、遺留分減殺請求権は、遺贈(遺言により相続人・相続割合を指定して遺産を相続させること)に限らず、被相続人による生前贈与にも適用されます。
仮に、生前贈与が被相続人によって複数以上の人に行われており、それらが遺留分侵害に該当する場合は、民法第1035条(贈与の減殺の順序)「贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする」、つまり、被相続人が亡くなった日に近い日時に行われた贈与分から、順次減殺していくことになります。
また、遺留分減殺請求は、侵害した相手が既に減殺の対象となる資産を第三者に譲渡していた場合でも、その権利を行使することが可能です。
民法第1040条第1項には、「減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる」とあります。
つまり、減殺請求を行うべき目的物が、既に遺留分を侵害した相手に処分されていた場合でも、遺留分権利者は目的物の処分価額の範囲内で弁償を受ける権利を有するのです。
特に相続財産のうち多くの割合を占める傾向のある不動産を目的物とする場合、侵害した相手は相続税納税資金確保のために早々に相続登記などを行い売却に動くことがあります。
当該不動産について仮に売買契約を締結・決済が終わっていたとしても、本条文を根拠に遺留分を侵害した相手に侵害分相当額を請求することが可能です。
なお、本条文は遺留分侵害の原因を「贈与」に限定しているように読めますが、遺贈についても類推適用されることは複数の判例で確認できます(最高裁判昭57.3.4、最高裁判平10.3.10)。
それでは、以下で遺留分減殺請求の具体的なステップを見ていきましょう。
当事者間で話し合い
遺留分減殺請求は、裁判所での調停や審判に先立ち、遺留分権利者と侵害者の当事者間で行うことが一般的です。
意思表示の方法については特段の規定がなく、基本的に口頭だけでも効力が生じます。
しかし、後日裁判所での調停や訴訟に至った場合を考慮し、その際の証拠のため内容証明郵便を用いることが望ましいでしょう。
相手方との話し合いがまとまらない場合、あるいは相手方が話し合いに応じる姿勢がない場合は、家庭裁判所への遺留分侵害請求の申し立てを検討することになります。
調停での申立(遺留分減殺による物件返還調停)
家庭裁判所における遺留分侵害請求の調停を、「遺留分減殺による物件返還調停」といいます。
遺留分減殺請求による物件返還調停は民事事件として扱われます。
また、日本では家事審判と同様に調停前置主義を採用しており、審判の前に必ず調停を行います。
遺留分減殺による物件返還調停は、必要書類を添えたうえで原則として相手方の居住地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
そして調停委員を交えた話し合いを行い、これが整い調停が成立すると、強制執行力を持つ調停証書が作成されます。
当該証書にもとづき相手方から申立人すなわち遺留分権利者に現物返還あるいは価額弁償の履行が為されます。
裁判・訴訟での申立
調停が不調の場合は、続いて遺留分減殺請求の訴訟を提起することになります。
この訴訟は、調停時の家庭裁判所ではなく、被相続人が亡くなった際の住所地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所(請求額が140万円以下の場合)に提起します。
審理の結果、和解に至り被告(相手型)の遺留分侵害を認める形で和解調書が作成された場合、または原告(遺留分権利者)の訴えを認める確定判決が下された場合、被告(相手方)には現物返還あるいは価額弁償履行の義務が発生します。
強制執行
相手方の遺留分侵害を認め、現物返還あるいは価額弁償を行う旨の調停が成立、あるいは裁判で和解もしくは判決が確定したのにも拘らず、相手方がその義務を履行しない場合は、強制執行の申し立てという手段があります。
遺留分の請求で気をつけたい点

兄弟姉妹には遺留分減殺請求権がない
遺留分権利者について、民法第1028条では「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける」と定めています。
つまり、遺留分減殺請求権が認められるのは「兄弟姉妹以外の(法定)相続人」、具体的には『法定相続人の配偶者(内縁関係および愛人を除く)』『子ども(養子を含む)』『孫(代襲相続が発生した場合)』『両親・祖父母(両親からの代襲相続が発生した場合)』が、遺留分が認められた相続人です。
兄弟姉妹に、遺留分減殺請求権は認めていられないのです。
遺留分が兄弟姉妹には認められていないということは、当該兄弟姉妹の代襲相続人となることが推定される甥や姪にも遺留分減殺請求権が認められないということになります。
遺留分を侵害した者が無資力状態の場合
仮に相続人の兄が相続人の遺留分を侵害していたとします。
しかし、その兄は減殺請求を行った時点で、侵害した遺留分を使い切っており無一文でした。
この場合、侵害された相続人は泣き寝入りするしかありません。
民法第1037条には「減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する」と規定されており、結局のところは遺留分権利者の損失となってしまうのです。
また、この規定により遺留分を侵害した兄の後順位の相続人である兄の子どもなどに対して遺留分減殺請求を行うことはできません。
遺留分減殺請求には時効がある
民法第1042条には、「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする」とあります。
つまり、遺留分減殺請求権は相続および遺留分の侵害があったことを知ったときから1年、または相続発生後10年を過ぎると時効となり、請求の権利を行使することが認められなくなるのです。
権利を放棄することもできる

被相続人に財産額を超えた借金があることが明白な場合、あるいは心情面や他の相続人との関係などで被相続人の財産を一切相続する意思が無い場合は、相続人には相続そのものを放棄する選択肢があります。これを相続放棄といいます。
相続放棄は被相続人の生前に行うことは認められておらず、相続発生後それを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所を通じて行うことと定められています。
一方で、遺留分については家庭裁判所の許可を前提に被相続人の生前でも放棄することが可能であり、相続発生後も特段の意思表示や手続き等を行わずに放棄できます。
まとめ
以上、遺留分の基礎についてご紹介しました。
遺言書を書く際は、各法定相続人間で遺留分の侵害が無いように全財産や特別受益分を可能な限り正確に把握したうえで、法定相続人に対する遺産分割割合を決めていただく必要があります。
また、遺言や遺産分割協議の内容などから自身の遺留分が侵害されているのではないかを感じた場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談したうえでご自身が受けるべき遺留分を把握し、しっかりとご自身の権利を主張していただければと思います。