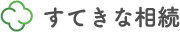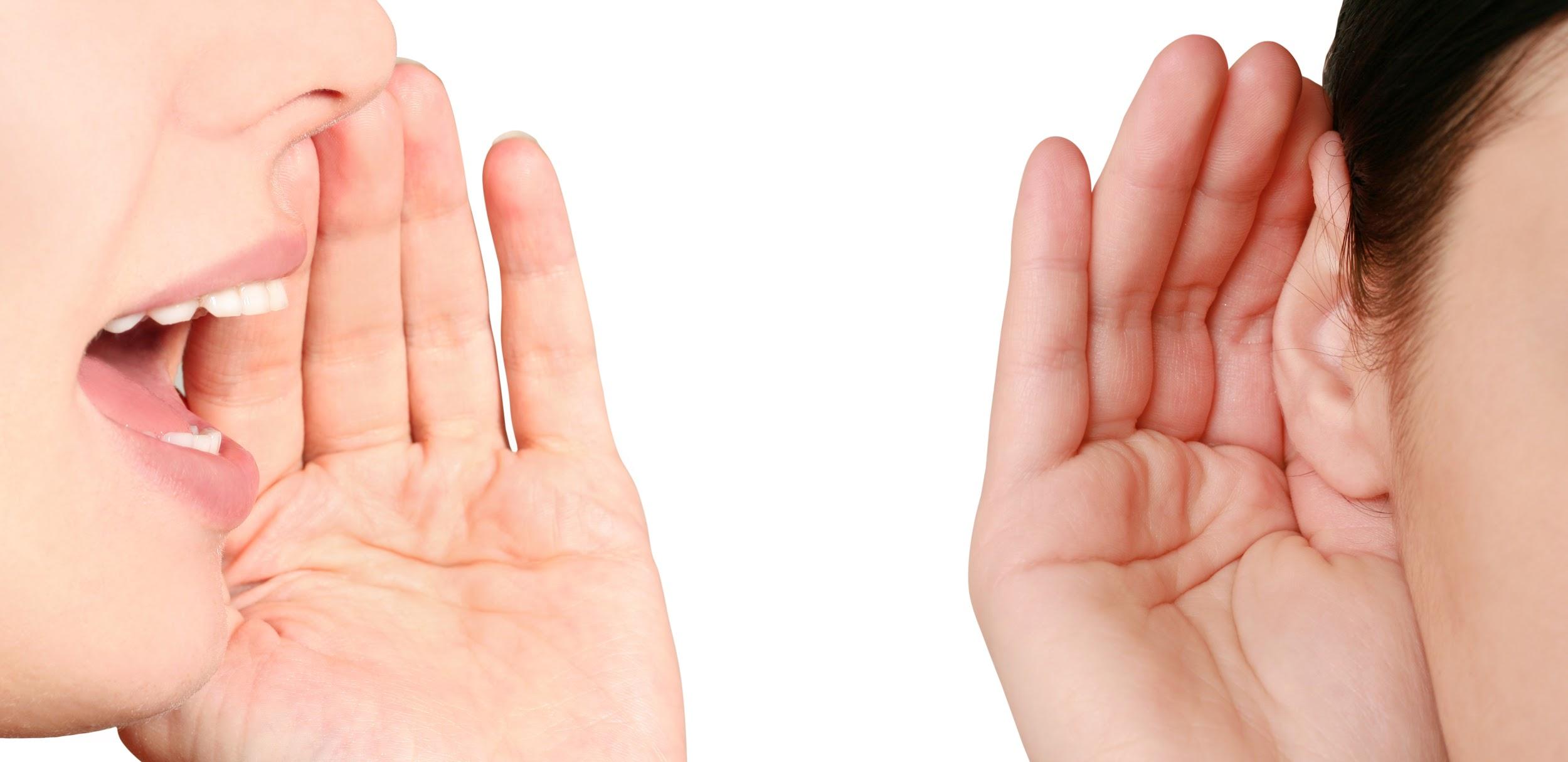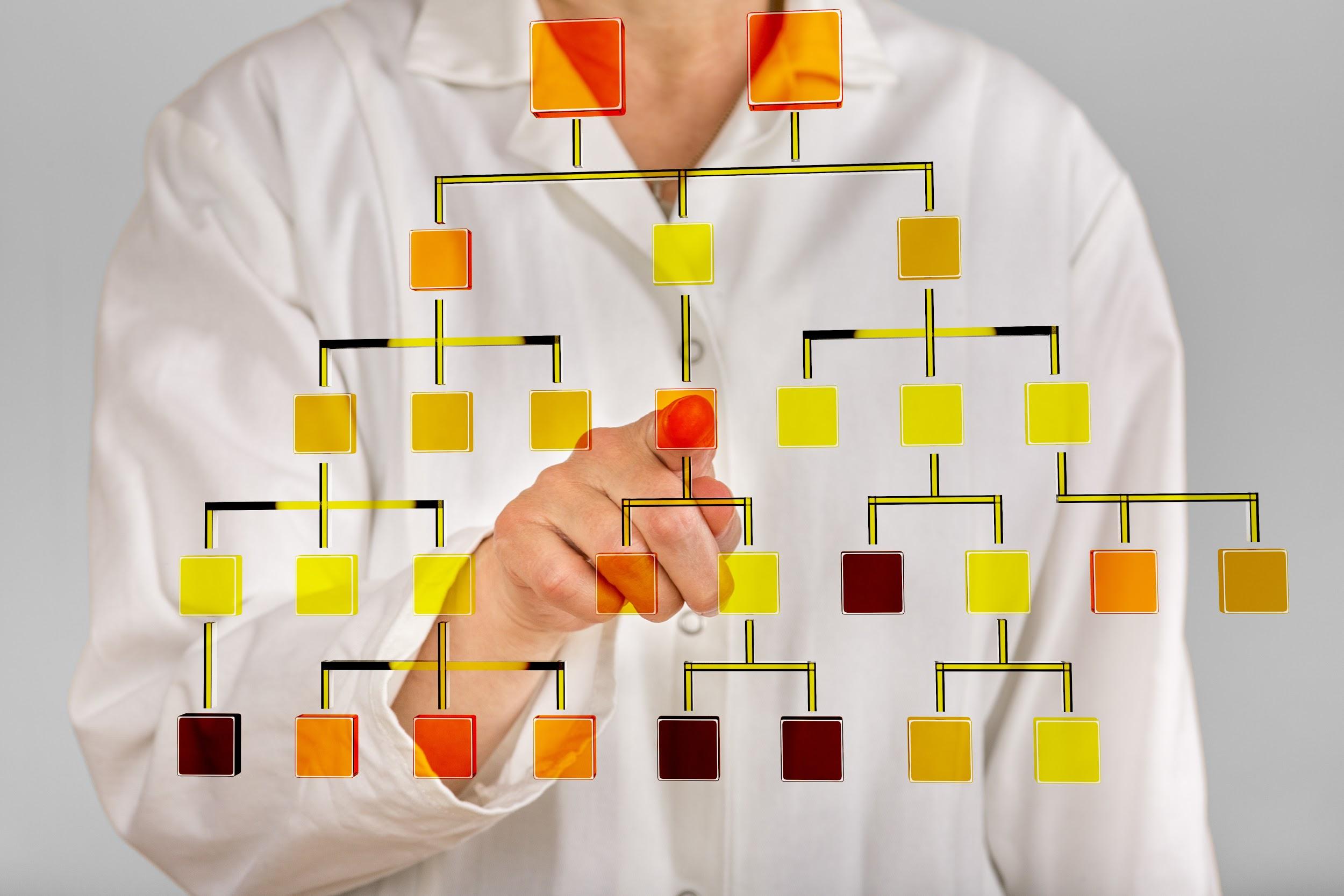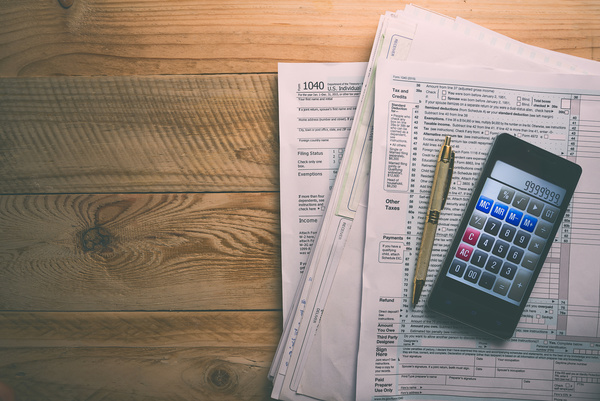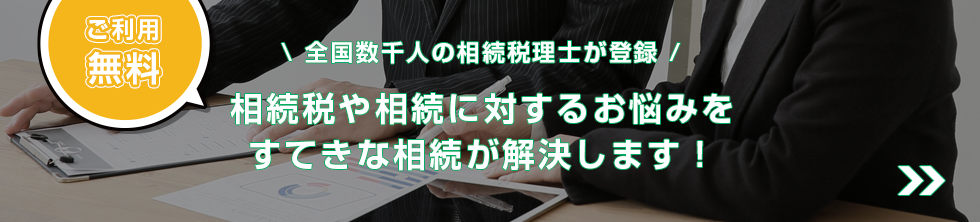-
カテゴリーで絞り込み
相続について基礎知識を説明しています。相続とは、相続の手続き、生前にできる相続対策など、相続について知っておくべき情報をまとめています。
相続と遺贈はどう違う?遺贈するための注意点も解説
終活という言葉が定着してきており、自分の身の回りを整理整頓するといった意識が高まってきました。
終活ノートと呼ばれるノートも一般的になっており、自分の死後について考える機会が増えてきたように思います。
自宅の整理整頓や近辺整理など、親族に迷惑がかからないように行動する方が多くなったのではないでしょうか。
そのようなことから、いざ整理整頓を始めると、
「家は誰に守ってもらおうか」
「貯金は誰にどれくらい残そうか」
「自分の財産だから、自分がお世話になった人や渡したい人に譲りたい」
と、決めなくてはならないことが多いことに気が付くと思います。
被相続人は法定相続人以外の第三者に自分の財産を承継したい場合、「遺贈」という方法を使って承継することができます。
一般的に財産を引き継ぐ場合は「相続」という言葉が使われますが、「遺贈」と「相続」はどう違うのでしょうか。
遺贈をしたい場合、どんな点に注意をすべきでしょうか。
詳しく紹介したいと思います。
相続とは?

相続とは被相続人が亡くなると、相続人に被相続人の財産が引き継がれることを言います。
預金や土地などプラスの財産だけでなく、ローンや借金などのマイナスになってしまう財産も相続されることとなります。
被相続人から財産を相続される相続人は「法定相続人」とよばれ、その立場によって相続順位が決まっています。
配偶者は常に相続人です。
配偶者以外の法定相続人の順位は、子及びその代襲者が1番目となります。
代襲者とは法定相続人が亡くなっている場合に権利が移る人のことをいい、被相続人の子がなくなっている場合は、その相続の権利が子供の子供、つまり孫に移っていきます。
孫も亡くなっている場合は、その子供である曽孫へと権利が移っていきます。
被相続人は遺言書で、誰に何を相続させたいか希望を残すことができます。
再婚前の妻との間に子供がいるなど家族関係が複雑で、遺産相続の分配でトラブルになりそうな時は、遺言書で希望を残すという手段が有効な場合もあります。
遺贈とは?相続とはどう違う?
法定相続人へ財産を譲る際、遺言書が用意されていない場合でも、法律で相続人や相続割合が決められているため、何もしなくても遺産が相続されます。
もし、あなたが法定相続人以外の第三者に財産を譲与したいとなった場合は、遺言書に「誰に何を遺贈したいのか」を明記することで、贈与をすることができます。
このように、法定相続人以外の第三者に、遺言書に記載することで遺産を承継することを「遺贈」と言います。
遺贈を法定相続人にすることも出来ますが、譲与するものによっては、手続き等が複雑になる場合があるので要注意です。
遺言書では法定相続人へは「相続」、法定相続人以外の第三者へは「遺贈」と使い分けをして、記載すると良いでしょう。
それでは、遺贈についてもう少し詳しく説明していきます。
遺贈の基礎知識
「遺贈」いう形で法定相続人以外の第三者に財産を残す場合、必ず遺言書を用意する必要があります。
遺言書を用意すること以外の方法で、法定相続人以外の第三者に遺贈することはできません。…


生活保護を利用している人は財産を相続することはできるのか?
生活保護制度は、「憲法25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という憲法に従い、国民の権利を守るための制度です。
この憲法に反しない行為、つまり生活保護受給者が財産を相続するという行為は、国の憲法上推進されるべき行為となります。
しかし、生活保護受給者の方々の生活は、多くの制度によって支えられているため、相続には特殊な行政手続きも発生します。
今回は、生活保護受給者が財産を相続するときの注意点や、手続き方法について詳しく解説していきます。
生活保護とは?対象となる条件とは
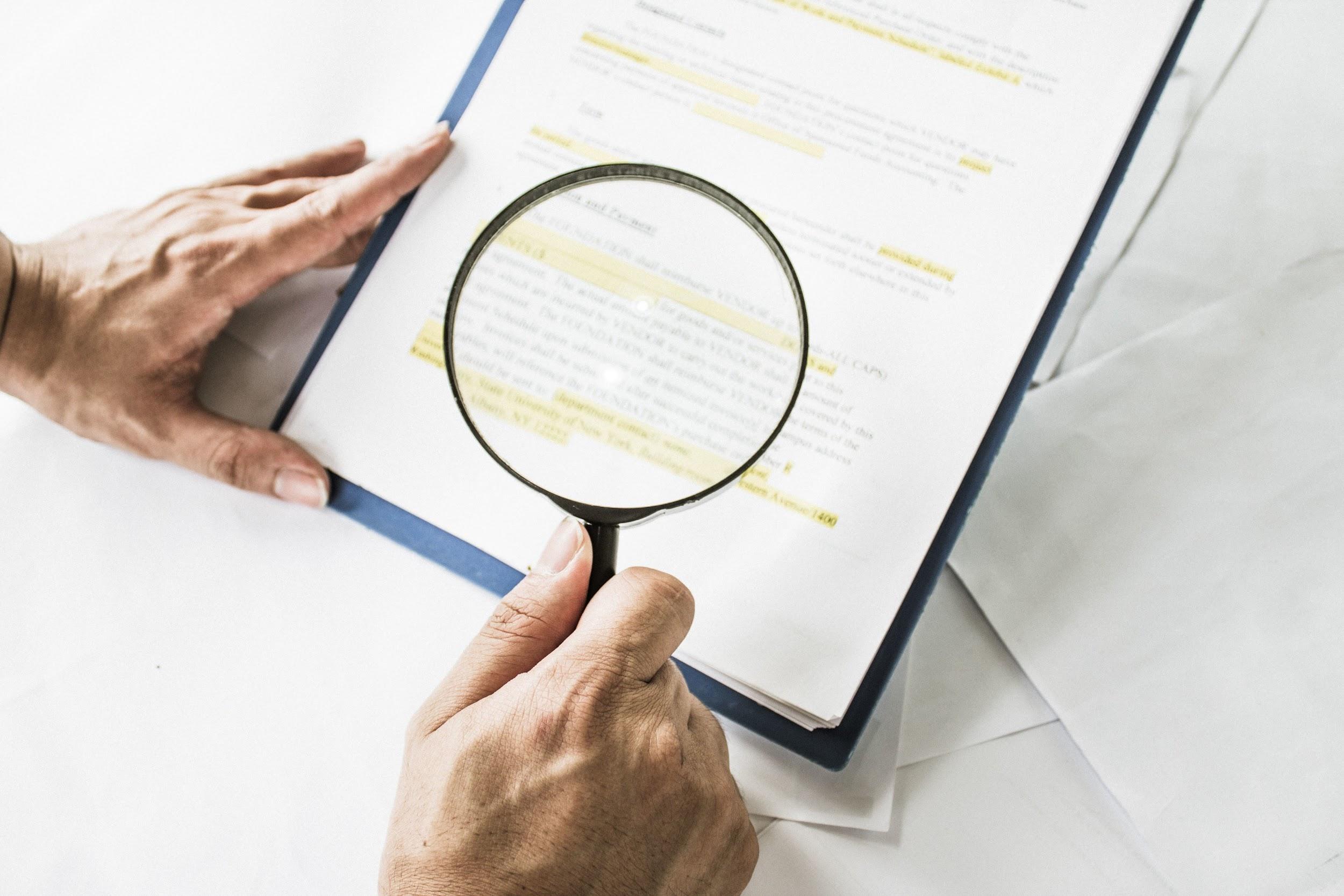
生活保護制度とは、福祉事務所や市区町村の個別判断によって対象者が決定し、対象者に生活保護費が支給される制度です。
まずは、生活保護制度の自立支援のための生活保護費を受給できる人の条件について解説します。
厚生労働省のHPには、生活保護の要件を次のように明記しています
| 生活保護の要件等(生活保護制度|厚生労働省より引用) |
| 生活保護は世帯単位で行い、①世帯員全員が、その利用し得る②資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために③活用することが前提でありまた、④扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。 |
ちょっと難解でわかりにくい文章ですから、簡単に書き直します。
| 生活保護の要件とは? |
| 生活保護は、世帯単位で行います(④)ので、扶養してくれる家族がいる場合は、家族に頼って下さいね。
援助をお願いできる家族(家族の所在・範囲の判断は市区町村の判断)がいない場合は、自分が働けるなら精一杯働いて(②)、持っている資産や財産がある(②)場合は、それらを全てお金に換えて(③)、福祉・労災・国民年金・厚生年金等、行政から、あるいは会社、保険会社からの支給等(②)、あらゆる手段を講じて(③)、少しでも生活向上の努力を自分なりに精一杯やって、自分なりに努力しましょう。 それでも生活に困窮する場合は、生活保護の受給の権利を利用して憲法25条の「健康で文化的な制定限度の生活」になるよう国が保護します。 |
上記の解説のように、①~④の要件の総合判断は、福祉事務所や市区町村の個別判断に委ねられています。
このように、できる限りのあらゆる手段を講じても、それでも生活に困窮している人に対し、国が考える憲法25条の最低限度の生活を送るために必要な金額の不足金額を国が支給してくれる制度が「生活保護費」なのです。
つまり、生活保護制度は、国民が憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」を一日も早く取り戻せるように、自立支援していく制度であり、生活保護で永遠に生活を保証してくれる制度ではないのです。
働けるのに生活向上の努力をしない人、貯蓄や収入がある人などは、生活保護費を受給できる資格がない者として、生活保護費を打ち切られてしまいます。
したがって、生活保護受給者は定期的に担当のケースワーカーの面談を受け、あるいは訪問調査を受けて、生活や収入の状況を報告する義務もあります。
つまり、行方不明になったり、音信不通になったり、健康なのに理由もなく会社を勝手に辞めて努力している状況が見られない人には、生活保護の受給がストップされることもあるのです。
生活保護の受給者が財産を相続すると?

生活保護の受給が原則停止または廃止になる
生活保護者が相続によって金銭的な余裕が生まれた場合、その金額によってそれぞれですが、生活保護費が削減・停止される可能性があります。
生活維持のための「あらゆるもの」の活用、という生活保護の要件の、「あらゆるもの」の中には、相続によって得た財産も含まれるからです。
相続によって少しでも財産を得たなら、預貯金ならそれを利用して、不動産等だったなら、それを売却、あるいは活用して、生活を向上することができると判断されるケースもあります。
相続によって生活が破綻する場合は相続放棄できる可能性も
相続したことによって、生活が向上するどころか、却って生活保護を打ち切られて、生活が困窮してしまうこともあります。
相続したものが、預貯金なら良いのですが、売却しないとお金にならない不動産や物品だった場合に多く当てはまります。
例えば、相続税のかかる山をいくつも相続して、その山を売却したくても買い手がつかなかったり、借地として土地を相続しても上物の建物が他人の持ち家だったりして、借地の賃料しか入ってこないような場合もあります。…